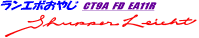 |
A license, manners, etc. menu powered by lan |
走行会の要領 オイルレベルゲージフックは付けましょう。抜けるとオイルが吹いて大変です。 ■用意するもの 
■クルマについて ノーマルだから走れない ということは無いと思います。エボ7以降のCT9Aの場合、状況によって差はあると思いますが純正ブレーキフルードが唯一心配だと思います。グレードの高いものに交換した方がいいです。それでもフカフカしてきますが、その時は無理せずクーリング走行しましょう。 タイム狙いでなければリミッター解除も特にしなくてもいいでしょう。メーター類は付けて楽しい?見て満足です。いじる毎に数値を比較して良し、あって損は無いと思います。ノーマルで全開にして温度やブーストがどういう推移をするか自分で把握しておくと後々参考になると思います。なお、温度については事実を記載していますが、トラブル責任は負いません。
■その他知っておいた方がイイこと
ライセンスの種類と取得について ■ ライセンスには、JAFの公式ライセンスと、それとは全く別にサーキットが発給しているコースライセンスというものがあります。 いわゆるAライやBライというJAF公式ライセンスが無いとサーキットを走れないと思っている方が時々いらっしゃいますがそうではありません。AライやBライは、JAF公式競技会に出るためのもので、JAF公式競技に出ないのであれば必要ありません。
■ 国内Bライセンスで出場できる公式競技は、ジムカーナ・ダートラなど1台で走る(スラローム競技)ものだけで、公式のレース(複数台が同時に同じコースを競争して走る競技)には出れません。JAF主催の講習会、もしくはJAF認定のイベントなどに出れば資格は取れます。申請代金は、テキスト代と合わせ¥9,000−位だったと思います。 ■ 国内Aライセンスは国内格式レースに出場できます。条件として、Bライセンスで出場できる公式競技に少なくとも1回の出場経験を必須とします。が、ノーライセンスでも1日でAライセンスまで取得できるイベントがあります。 どういうことかというと、そのイベントで 講習→Bライ取得→公式競技→Aライ講習(フラッグレクチャーなどの実技も含む) がイベントの中に全て含まれるものです。 そういったイベントは走行料金も含まれていますので値段はそこそこで違ってきますが、ノーライセンスの場合¥45,000−位、Bライ所持者は¥35,000−位で取得できると思います。ジムカーナなどに日頃から参加されている方であれば、純粋なAライ講習会(¥20,000−位?)に参加されれば済みます。 また昔と違い、JAF加盟クラブに籍を置かなくても毎年のライセンス更新が出来る様になっています。 ■ それに対し、コースライセンス(サーキットライセンス)はサーキットそれぞれが独自に設定しているものです。 これもサーキットを走るのに絶対必須というものではありません。サーキットでイベントなどが何もない時にコースを一般に開放する時がありますが、その練習走行枠を走らせてもらえるための会員証みたいなものです。 ですから、ショップなどが主催する走行会はもちろん、サーキット主催のイベントでもコースライセンスは通常必要ありません。 サーキットによって、その位置付け・取得代金も様々ですので、以下に例を紹介します。 上写真の中央はオートポリスで、まさにコースライセンスです。公認サーキットだけあって取得金額も高いです。特別なレースが開催されていない時などの入場料などが無料もしくは割引になったりする特典もあります。これを持っていると、25分一枠を安価で走れます。 上写真の右はHSRサーキットで、コースライセンスというよりも説明修了証という位置付けです。取得金額はなんと\500-!!(カード作成実費程度です。)これを持っていると、25分一枠を\4,200-(少し高い気がしますが)で走れます。計測器はプラス\1,050-で、希望により走行タイムをHSRに公式登録でき、結果はタイムバトルに反映されます。 HSRは本来テストコースであるがために、近所(でもないですが)に住んでる私達は安く走れてラッキーです。トリッキーなレイアウトに加え、昔は200km/hオーバーも体験できる実に立派なコースでした。全国的にはあまり知られていないかもしれませんが地元では人気です。 旗の説明 以下の説明は走行会などでよく使用される場合の意味を紹介しています。モータースポーツ法典記載の正式なものではありません。また、実際によく使われるのはチェッカー・黄旗・赤旗・オイルフラッグの4つだけという場合がほとんどです。 但し、Aライ取得時にはこれら旗を使った実技試験があります。オレンジボール+ゼッケン番号などを出されて気付かずに素通りすると試験に落ちます。 (技術的な試験は無く、旗の指示を守れるかどうかだけです。)
サーキットマナー他 ■マナー
|



